抑うつ性障害(うつ病)
二十人に一人がうつ病と言われ、その数は六百万人にも達するとされます。
女性では、四人に一人が、生涯の間にうつを経験するとも言われています。それほど、うつは身近な問題なのです。
元々うつになりやすいとされる更年期や高齢者だけでなく、働き盛りの世代や若者世代、さらには子どもでも、うつが非常に増えています。
うつの症状は大きく、軽症のうつにもみられる症状と大うつ(症状の重いうつ)に特徴的な症状に分けられます。
①気分がふさぎがちになり、悲観的な考えにとらわれる。
②やる気が低下し、体が疲れやすい。
③食欲や性欲が低下する。逆に、過食になることもある。
④自信や自己有用感が低下する
⑤判断力や集中力が低下する
⑥もうダメだと絶望的な気持ちになる
⑦夜が眠れなかったり、朝が起きられない
大うつは、重症のうつ状態という意味です。
うつという場合、まず小うつか大うつかを見分ける必要があります。
大うつの場合は、自殺の危険も高く、早く治療を開始することが必要だからです。
大うつの場合には、薬物療法が必要なケースが多いと言えます。現在は、とても優れた薬があり、一日も早い治療をお勧めします。
それに対して、小うつの状態は、本人は苦しんでいるものの、まだそれが体や脳の機能を顕著に低下させるところまでは至っていない状態です。
今の段階なら、適切な手立てによって、速やかにうつから脱出できます。薬物療法も必要ないことが多く、むしろ心理的な問題や環境的な問題が大きいケースがほとんどです。
しかし、放置したり、我慢していると、次第に大うつに移行することもしばしばです。
うつにもタイプがある
深く落ち込み大うつになるタイプとしては、メランコリー型うつ病と躁うつ病があります。
メランコリー型うつ病は、生真面目で、律儀な性格の人に多く、中高年によく見られます。
それに対して、躁うつにともなううつは、朗らかで活動的な人に多く、若い頃からうつが始まっていることが多いと言えます。
それ以外にも、過食や過眠をともない、傷つくことや見捨てられることに過敏な傾向を示すタイプに非定型うつ病があります。これも、躁うつの一種ではないかとも考えられています。
一方、比較的軽い落ち込みである小うつが見られるタイプとしては、環境の変化やストレスの増加に伴って生じる適応障害や、くよくよ悩みやすい性格の人が、慢性的に小うつを繰り返すディスチミア(気分変調症)があります。
最近、よく耳にする「新型うつ病」は、仕事を前にするとうつ症状が強まるが、好きな遊びや趣味のことになると元気がでるというタイプで、本態は適応障害だと考えれます。
仕事に対して不適応を起こしている面が強いと思われます。
うつ病として治療すると、むしろ症状が固定化する場合もあります。適応障害として治療した方が、良い回復が得られやすいのです。
「うつ」にひそむ「躁うつ」
うつの診断で気をつけなければならないのは、うつと思われていたのが、実は躁うつ(双極性障害)だったということが少なくないことです。
最近では、うつの半分くらいが、実は躁うつだということがわかってきました。
特に、四十歳までのうつでは、躁うつがひそんでいることが多いのです。
抗うつ薬をのんで調子がよくなったと思っているうちに、逆に躁になってしまうこともあります。
若い人のうつや出産後のうつでは、躁うつが隠れていることが多いので、気分の波がないかをよくチェックする必要があります。
また、抗うつ薬がなかなか効かないという場合にも、実は躁うつだったということがあります。
うつだけが見られる単極性うつ病と、躁とうつが見られる双極性障害では、治療の仕方が違うので、両者を見分けることが重要です。
メランコリー型うつ病とその治療
かつて内因性うつ病と呼ばれ、最近では、メランコリー型うつ病とか、大うつ病と呼ばれるタイプで、症状が重い本格的なうつ病です。遺伝的要因がある程度強いと考えられています。
このタイプ、かつては、代表的なうつ病でしたが、近年では、うつ病全体に占める割合は、一~二割にまで下がっています。
内因性律儀な性格の人が、中高年からうつになり、真夜中に目が覚めて眠れず、食欲も落ちて体重が激減しているという場合には、ほぼ間違いなく、このタイプのうつ病だと言えるでしょう。
メランコリー型うつ病の場合には、自殺の危険が高いということを、まず念頭に置いて、ある程度回復するまでは、目を離さないように気をつけておくということが必要です。
それが無理な場合には、入院も考慮する必要があります。
自殺しないことを約束してもらうことも大事です。律儀な性格の人が多いので、約束を守ろうとするので、しっかり約束をしておくことは自殺抑止につながります。
治療としては、抗うつ薬を中心とする薬物療法がもっとも有効です。
SSRIやSNRIが第一選択ですが、中には、効果が十分でない場合がある。ことに年齢の高い男性では、SSRIやSNRIが奏功しにくいと言われています。
その場合には、三環系抗うつ薬とよばれるタイプの抗うつ薬が有効なことが多いのですが、ただ、三環系抗うつ薬は、口渇や便秘などの副作用が強いのが難点です。
不眠やイライラなどの症状は早い段階でよくなりますが、意欲低下や集中力などは、回復に時間がかかります。
元気なときの比較して、調子が悪いと思いがちですが、悪かったときと比較して、良くなった点に目を向け、のんびり気長に療養することが、良い結果につながります。
若い人では回復も早いですが、その場合は、双極性がひそんでいるという場合もあります。
中高年のうつでは、一般に考えられているより、回復に時間がかかるのが普通です。
一つには、ストレスを抱えたまま回復をはからなければならないということがあります。
また、中高年のうつでは、治療を開始した時にはかなり症状が進んでいて、脳の委縮が始まっているということも珍しくないためです。そうなる前に、早く治療を開始したいものです。
運動はとても効果的です。すぐに効果が現れるというよりも、長期的に続けることで、本当の回復効果が得られてきます。
ディスチミア型うつ病とその治療
うつの中には、比較的軽いうつ状態が、長年にわたって続くタイプがあります。
気分変調症(ディスチミア)とかディスチミア型うつ病と呼ばれるタイプです。
メランコリー型に比べると、症状が軽度で、食欲や体重、体の動き、頭の働きといった面での低下は軽度です。
「うつでつらい」「気分が晴れない」と、本人が感じる主観的な症状は強いのですが、それに比べて、客観的な症状はあまり目立たず、一見したところでは、それほど病気には見えないという点も特徴です。
このタイプは、性格的な要素も強いと考えられています。
神経質で、自信がなく、不安の強い性格との結びつきがみられ、「抑うつ神経症」と呼ばれていたこともあります。
活気が乏しく、疲れやすく、絶えず悲観的な考えに囚われ、楽しいことよりも、つらいことや苦しみばかりを感じて、溜め息ばかりついているというタイプです。
ネガティブな思考パターンが染みついていて、どんなことも悪いようにばかり考えてしまう傾向が強いと言えます。
親子関係に問題を抱えている人に多いといった点も特徴です。
したがって、ディスチミア型うつの場合は、薬を飲んだからといって、それで回復というわけにはいきません。
確かに、うつや不安の症状はやわらげることができますが、ネガティブな思考パターンや不安定な親子関係がそのままだと、薬を飲んで、一時的に良くなっても、また何かあるごとに揺れるということを繰り返しやすいのです。
根本にある問題を解決せいずに、症状だけ薬で取り去ろうとすると、薬物に依存するだけで、どこか現実逃避的な生活を続けてしまうということになりがちです。
本当の意味での改善のためには、親子関係の問題と結びついた、ネガティブな思考パターンを修正することが必要で、そうした視点での治療が必要です。
気分変調症の一般人口での有病率は約三~四%と言われ、頻度の高い疾患です。その四割は、罹病期間が十年以上の長期にわたる。
女性の頻度は、男性の約二倍です。半数以上が、何らかのパーソナリティ障害を合併しています。
不安障害や大うつ病の合併も四割以上と高く、大うつ病と合併したときは、ダブル・デプレッション(二重うつ病)と呼ばれます。
若い頃から、気分変調症がある人では、将来、ストレス要因をきっかけに大うつ病になりやすいと言われています。
十代から始まるケースも多いですが、三十代、四十代になって始まることもあります。
大うつ病との違いは、日常生活や社会生活がどうにか維持されているケースが多いことです。
薬物療法もある程度は有効で、SSRIなどの抗うつ薬で改善が期待できます。
ただ、一部に「躁転」するケースがあることが知られており、双極性障害がひそんでいることがあります。
その場合には、気分安定化薬との併用が必要です。
適応障害と他のタイプを見分けるポイント
もう一つのタイプは、適応障害を起こしたときにみられる「うつ」です。反応性うつ病という言い方をすることもあります。
職場や学校といった環境からのストレスが原因で、一過性のうつ状態を引き起こしたものだと言えます。
ただ、何かがきっかけで、うつになるという場合でも、適応障害だとは限りません。
メランコリー型うつ病やディスチミア型うつ、さらには、双極性うつ病でも、何かのきっかけにうつになることは多いからです。
どうやって見分ければいいのでしょうか。
見分ける上で、重要なポイントの一つは、ストレスとなっている環境から離れると、症状が良くなるかどうかです。
適応障害の場合には、ストレスとなっている問題を解決するか、職場や学校を替わるかすると、元通りに元気になります。
新しい環境に慣れて、元気を回復するということも多いのです。
通常、六か月を基準として、それまでに回復した場合は、適応障害とみなすというのが一般的ですが、ストレス源がそのままであれば、適応障害であっても、六か月以上症状が続いてしまうということは、しばしばです。
では、他のタイプのうつと、どこで見分けるのでしょうか。
もう一つのポイントは、症状の重さと、それまでの経過です。
適応障害でみられるうつ状態は、小うつであり、精神身体症状を伴わないのが普通である。
もし、体重の顕著な減少(増加)、動きが緩慢、頭の回転が鈍く、集中できないといった症状が強く見られる場合は、小うつではなく大うつを呈しており、メランコリー型うつ病か、双極性うつ病が疑われます。
中高年であれば前者、若い人であれば後者の可能性が高いと言えます。
一方、ディスチミア型の場合には、小うつという点では似ていますが、以前からネガティブに考え、沈むことが多かったというのが普通です。
もちろん、もともとディスチミア型うつを抱えていた人が、新しい環境になじめず、さらに適応障害や大うつ病を起こすという場合もあります。
適応障害の治療と克服
適応障害の治療、克服には、二つの方向があるということになります。
一つは、不適応を生じている環境の問題を解決したり、ストレスに対する耐性を高めて、不適応を克服し、その環境で支障なく生活できるようにするという方向です。
もう一つは、合わない環境から、できるだけ早く離れて、その人に適した環境に移ることで、新たな環境での適応を図るという方向です。
職場や学校で適応障害を起こしたという場合、どちらの方向を方針に据えるかということが重要になります。
通常は、まず不適応を克服するという方向で支援し、どうしてもうまくいかないという場合、環境を変えるという方針に切り替えるわけです。
合わない環境にしがみつこうとして、ダメージが大きくなってしまうというケースがこれまでは多かったのですが、最近は、見切りが早過ぎるというケースが目立ちます。
確かに、それで病状が深刻化するということは防げますが、困難や試練を乗り越える粘りや抵抗力がつかないという難点もあります。
厭なことがあっても、それを乗り越える努力も、ある程度は必要だと言えるでしょう。
そのために重要になるのが、次の二つの点です。
一つは、生じている問題を解決することです。
そして、もう一つは、ストレスに対する耐性を高めることです。
ただ、問題を解決する能力をすぐに高めることは簡単ではありません。
ことに適応障害を起こして、うつになっているときには、なおさらです。
そういう場合にもできることは何でしょうか。
実は、問題を解決する能力を左右する上で重要な要素は、他の人に相談できるかどうかなのです。
相談することができれば、問題解決能力は格段に高まります。
ところが、問題解決が苦手な人ほど、自分だけで何とかしようとしがちです。自分の弱みを見せ、相談するのが苦手な人ほど、適応障害を起こしやすいのです。
したがって、まず実践したいのは、問題や支障が起きたら、適切な相手に相談するということです。
適応障害を起こしている場合には、そのことが特に重要になります。
問題の解決を、第三者に頼らざるを得ないのが普通だからです。
自分でどうにかなっているのなら、そこまで追い詰められてはいません。今こそ、誰かに頼る時なのです。
他の人に問題解決を助けてもらうことを、恥ずかしがったり引け目に思う必要はありません。
それよりも、自分だけで抱え込んだまま潰れてしまう方が、ずっと恥ずかしいと思うべきです。
もう一つのポイントであるストレス耐性を高めるという点では、何ができるでしょうか。
人に相談することも、ストレスを半減させます。どんなことでも話せる家族や友人がいる人は、幸運です。
実際、そういう人がただ話を聞いてくれるだけで、ストレスは大幅に緩和し、自殺のリスクも低下します。
ストレスに強くなるという点で、もう一つ大事なことは、期待値を下げるということです。
人は、自分が望む期待値と現実のギャップだけ、フラストレーションを感じます。期待値が高ければ高いほど、同じ現実に遭遇しても、落胆やストレスも大きくなってしまいます。
実際、完璧主義な人は、適応障害を起こしたり、うつになりやすいのです。百点をいつも目指していると九十点でも、不満足な結果でしかありません。
いつも人に愛されたい、認められたいという承認欲求が強すぎる人は、人から些細な非難を受けただけでも、強い不安にとらわれてしまいます。それもまた、適応を阻害します。
百点ではなく五十点で満足する。みんなから評価されることは期待するより、自分を評価する人もいれば、評価しない人もいて当然だと思う。
実際、優れた人ほど、風当たりも強くなり、中傷も増えます。中傷は、存在感の裏返しだと思っておけばよいわけです。
ストレス耐性を高める上で、もう一つ大切なことがあります。それは、切り替えを上手にするということです。
適応障害に陥り、うつになったときというのは、自分が躓いた問題や降りかかってきた難題に、とらわれてしまった状態になっています。
そのことを絶えず考え続け、切り替えてリラックスすることができないのです。
言われた言葉や心理的衝撃を頭の中で引きずり続け、その言葉や場面が反芻し続けてしまう。これを反芻思考と言います。
反芻思考に陥りやすい人は、うつにもなりやすい。日頃から、反芻思考を防ぐ習慣を作っておくことも大事ですし、反芻思考に陥ったとき、それを切り替える方法を知っておくことも大事です。
まず心掛けたいのは、日頃から、切り替えの訓練をしておくことです。
切り替えの方法として、簡単でけど有効なのは、体を動かしたり、場所を移動することです。
職場から出て、自宅に帰る。三十分以上の時間がかかった方が、切り替えには効果的です。
その間も、いつも習慣にしていること(音楽を聞く、本を読む、情報をチェックする)をするのも良いでしょうが、瞑想したり仮眠をとると、さらに切り替えは進みます。
自宅と職場が近いという場合は、自宅にまで職場での気分を引きずりやすい。
その場合は、意図的に徒歩や自転車で通うなどして、ある程度時間をかけると同時に、運動の要素を採り入れて、切り替わりを助けるとよいでしょう。
双極性うつ病を見分ける
同じうつでも、双極性障害に伴う「うつ」の場合には、抗うつ薬による治療が逆に問題をこじらせてしまいます。
もっとも問題なのは「躁転」という現象である。うつ病だと思って、抗うつ薬を飲んで快調になり、よくなったと思っているうちに、快調になり過ぎて、躁状態になってしまう現象です。
また、気分の波が激しくなり、躁とうつの周期が短くなったり(ラピドサイクラー化という)、抗うつ薬によって過激な行動化を引き起こし(アジテーションという)、ときにはそれが自殺企図に至る場合もあります。
このアジテーションによる自殺の問題は、若い世代ほど起きやすく、二十五歳より下の年齢層では、抗うつ薬の使用には、かなり注意が必要です。
元々気分の波があるケースでは、うつだと思っていても、実は、躁うつだということが少なくありません。うつの半分くらいは、実は双極性だということがわかってきました。
特に若い人のうつでは、躁うつ(双極性)の割合が高いのです。
躁うつ(双極性)のうつと、本来のうつ病(単極性という)では、まったく治療の方法も経過も異なるので、その点を念頭においておく必要があります。
双極性のうつと単極性のうつ病を見分けるポイントとしては次のような点が挙げられます。
- 若い人のうつ、三十代までのうつでは、双極性が多い。
十代から始まったようなケースでは、さらに双極性の可能性が高い。
単極性のうつ病は、四十代以降始まることが多い。 - もともと元気で、明るく陽気な性格の人が、うつになったという場合には、双極性が多い。
若い時からくよくよ悲観的にばかり考えるという人では、気分変調症が多い。
単極性うつ病では、生真面目で律儀で、責任感が強く、勤勉なタイプの人が多い。 - うつになると、寝る時間が長くなるといたタイプのうつでは、双極性が多い。
単極性うつ病の場合には、早くから目が覚めて眠れなくなることが多い。
双極性では、うつになると、体重が増える傾向を示すことが多いのに対して、単極性のうつ病では、減少することが多い。 - 何か楽しいことや、興味のあること、良いきっかけがあると、少し気分が良くなったり、また最初は気乗りしないが取り組んでいるうちに、気分がましになるという場合には、気分反応性があると言って、双極性であるか、小うつ(気分変調症や適応障害など)であることが多い。
単極性のうつ病では、気分反応性がまったくなくなるのが特徴です。 - もう一つ、とてもわかりやすい指標があります。それは、口数が多いか、少ないかということです。
双極性のうつでは、うつ状態でも、口数はそれほど減らず、苦しさを積極的に訴えることも多い。
一方、単極性のうつ病では、極端に口数が減り、電池切れのロボットのように、反応が乏しくなる。
返事が帰って来るのにも、長い時間がかかる。
よく喋るうつという場合には、双極性や気分変調症などの可能性が考えられます。
岡田尊司『うつと気分障害』より
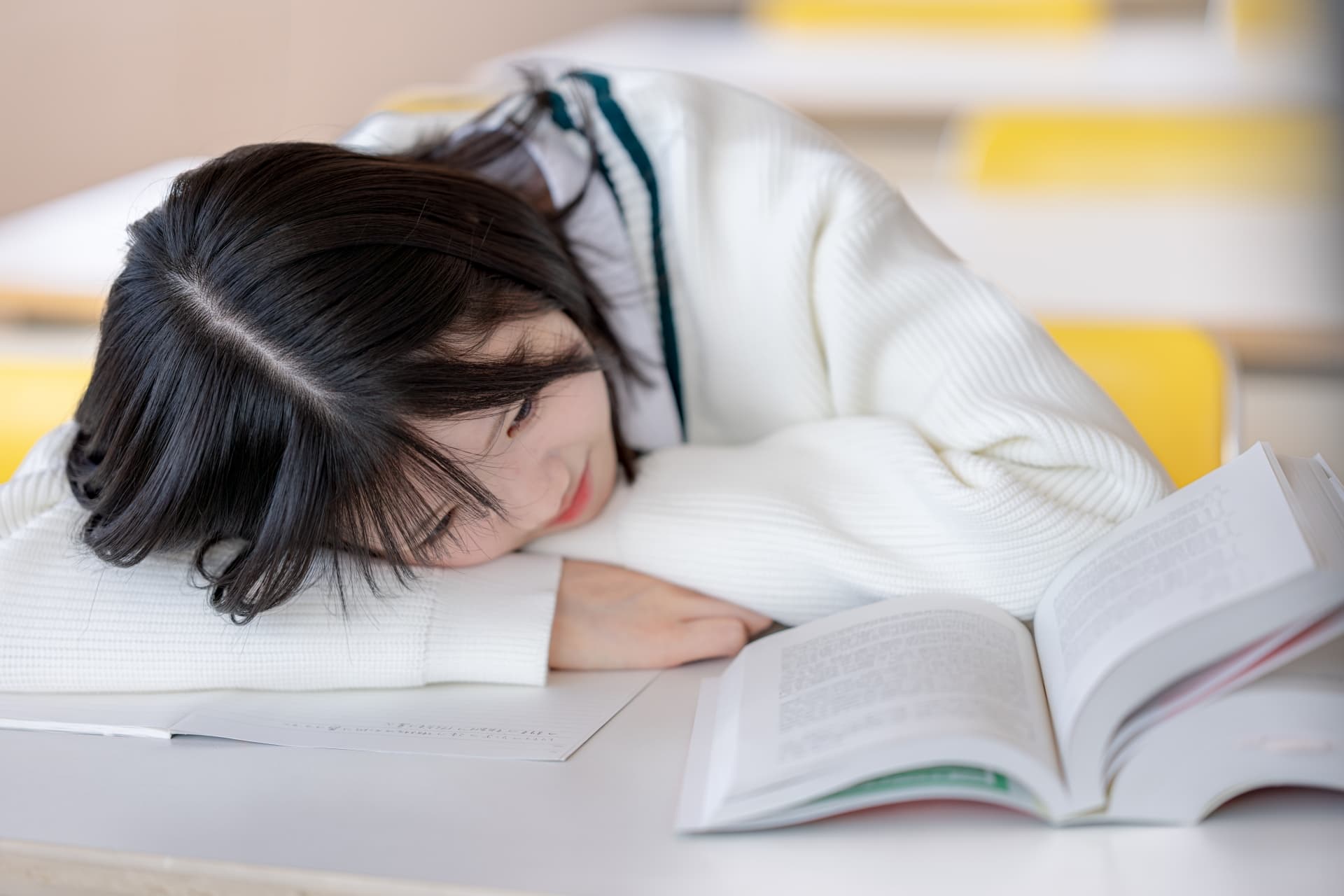
コメント